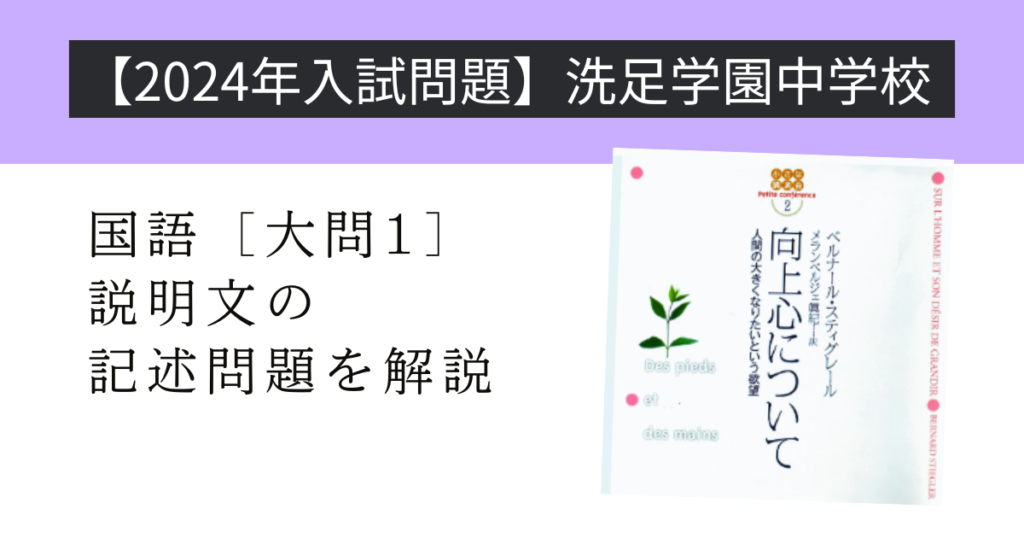
洗足学園中学校は、神奈川県川崎市にある中高一貫の女子校です。新約聖書に書かれているキリストの言葉から「洗足」と命名しました。創立1923年と長い歴史を持ち、音楽教育などにも力を入れていることで知られています。
2024年度の説明文は『向上心について―人間の大きくなりたいという欲望』(著:ベルナール・スティグレール)が出題されました。この文章では、宗教や信仰、哲学の歴史的な関係をひもときながら、現代社会における「信じること」や「欲望のあり方」について論じています。哲学的な内容で、小学生には少々難解な部分もありますね。
文章の概要
要約
宗教はかつて人間社会の中心的な役割を果たしていましたが、近代化や合理化が進む中で「神は死んだ」とされる時代に突入しました。この結果、人々は新しい信じる対象を見つける必要に迫られています。特に現代の資本主義は、未来を信じる「信用(クレジット)」の上に成り立っているため、信じる気持ちの喪失が社会全体に深刻な影響を及ぼしています。著者は、資本主義が欲望さえも計算可能なものとして扱うことで、欲望本来の力が損なわれ、人間の成長や社会の豊かさが失われていると指摘します。そして、「計算で収まらないもの」を求める欲望こそが、人間を高め、社会を再構築する鍵になると述べています。
難しい語句の解説
- 宗教(しゅうきょう):神や仏などの超越的な存在を信じ、それに基づいて行う信仰や儀式、生活のこと。
- 哲学(てつがく):物事の根本的なあり方や意味を探求する学問。
- 敬虔(けいけん):神や宗教に対して深い尊敬の念を持ち、真剣に信仰を行うこと。
- 弁論(べんろん):自分の意見を理論的に述べること。相手を納得させるために話をすること。
- 観念(かんねん):物事についての考え方やイメージ。
- 存在論的神学(そんざいろんてきしんがく):「存在」という考え方を通じて、神について考える学問。哲学と宗教を結びつけた考え方のひとつです。
- 一神教(いっしんきょう):唯一の神を信じる宗教。例としてキリスト教やイスラム教が挙げられる。
- 投獄(とうごく):犯罪などで捕まった人を牢屋に閉じ込めること。
- 資本主義(しほんしゅぎ):お金や商品を使って利益を得ることを目的とした社会の仕組み。企業や個人が自由に商売をして経済を動かします。
- 合理化(ごうりか):物事を理にかなった形に整えること。または、その過程。
- 創始(そうし):新しい物事や考え方を初めて作り出すこと。
- ニヒリズム:「何も信じられない」「すべてが無意味だ」と考える立場。虚無主義とも言われる。
- 確固(かっこ)としたもの:今ここに形として見えなくても、私たちの生き方や信念によって存在する、揺るぎない価値や意義のこと。
- イスラム教:神(アッラー)を唯一の神として信じる宗教。預言者ムハンマドを通じて伝えられた教えを大切にします。
- ユダヤ教:神とユダヤ民族の契約を信じる宗教。キリスト教やイスラム教の元になった教えを含んでいます。
また、文章に挙げられている哲学者についても、簡単に解説してあげるのが良いでしょう。
- ソクラテス:紀元前5世紀のギリシャの哲学者。人々に「本当の知恵とは何か?」を問いかけることで考えさせる方法(対話法)を用いました。弟子にプラトンがいます。
- プロタゴラス:紀元前5世紀のギリシャの哲学者。人間の感じ方や考え方が真実を決めるという「人間が万物の尺度」という考えを提唱しました。
- プラトン:ソクラテスの弟子で、哲学の歴史に大きな影響を与えた古代ギリシャの哲学者。「理想」と「現実」を分けて考える方法を編み出した。
- カント:18世紀のドイツの哲学者。「人間が何を知ることができるか」を考える哲学を確立しました。人間の理性や道徳について深く研究しました。
- ディドロ:18世紀のフランスの哲学者で、百科事典を編集したことで有名です。また、神の存在を信じない無神論を主張しました。
- ニーチェ:19世紀のドイツの哲学者。「神は死んだ」と述べ、人間が自分自身の価値観を作り出す必要性を訴えました。
重要問題解説 問2・問5
今回は、記述問題の解説をしていきます。文章の内容を理解することが難しかったので、記述で苦労した子も多かったのではないかと思います。ぜひ参考にしてみてください。
(問2)記述問題 ―線(2)「宗教への回帰という現象が起こっている」とありますが、本文によれば、これはどういう「現象」ですか。
■(問われていること)を確認する
この問題では「どういう『現象』ですか」と問われています。「どういうこと」と問われている問題は、言い換える問題です。「宗教への回帰」という表現を、具体的に言い換える問題であることを確認しましょう。
■(問われていること)に対する短い解答[記述の核]を考える
記述問題のポイントは、(問われていること)に短く答えることです。これを[記述の核]と言います。[記述の核]をつくるため、「宗教への回帰」という言葉が、文章中のどこで説明されているか探していきましょう。
「宗教への回帰」とは、どういう意味でしょうか。文章中のどこにこのような記述があるか見つけるため、―線(2)がある段落の構成を整理していましょう。
[―線(2)の前の段落]
①信仰が失われた社会では欲望も失われるため「宗教への回帰」が起こっているのかもしれない
②現代の資本主義社会は「信用(クレジット)」で成り立つのに、信じられるものがない
③だから、昔の信仰に戻ろうとする人たちがいる
①で「『宗教の回帰』が起こっているのかもしれない」と筆者の考えが述べられています。
②では、現代の資本主義社会の問題点が挙げられています。そして、③で「昔の信仰に戻ろうとする人たちがいる」と、筆者の考えをもう一度述べているのです。
このことから、[記述の核]は以下のようになります。
[記述の核] 昔の信仰に戻ろうとする現象
■[記述の核]に文をつけ加え、記述を完成させる
[記述の核]にの前半に、文をつけ加えれば記述を完成させることができます。
つけ加える文は ①対比 ②原因 ③説明 のどれかを、状況によって選択しましょう。
①対比 → 2つのものを比較する書き方です。「○○だったが」
②原因 → [記述の核]の原因を記述します。「○○だから」
③説明 → [記述の核]を詳しくする文をつけ足します。「○○くらい」「○○という」
今回は、「宗教の回帰」が起こっている③理由 が説明してあるので、理由を前半に書いていきましょう。青マーカー部分が、理由を説明した部分です。
[正答例]
資本主義社会は信用を前提に成り立っているのに、現代は何もかもが疑わしい時代で、未来を信じることもでいないから、昔の信仰に戻ろうとしている現象。
(問5)記述問題 ―線(5)「神が死んでしまった現代においては信じる対象になりうるのは、やはり〔神がかつてそうであったように〕別の次元を構成しているものだ」とありますが、ここでいう「別の次元を構成するもの」とはどういうのもですか。
■(問われていること)を確認する
この問題で「どういうものですか」と問われています。これも言い換えのもんだいであることがわかります。「別の次元を構成するもの」を、言い換えるために、文章のどこに注目したらよいか、迷った人が多かったのではないでしょうか。詳しく解説していきます。
■―線部を含む一文に注目する
ポイントは、―線部を含む一文を注意深く読むことです。
[本文]―線部を含む一文
そして、神が死んでしまった現代において信じる対象になりうるのは、やはり〔神がかつてそうであったように〕別の次元を構成しているものだと私は思うのです。
「そして」とは、添加の接続語です。これは、前の内容に新たな内容をつけ加える時に使われます。前の段落の文に注目してみましょう。
[本文]―線(5)の前の段落の文
神は自然の中にいるわけではないし、時間の中にもいないし、空間の中にもいない。なのに神は、時間と空間の中に生きる存在にとって不可欠なものなのです。
この部分を要約すると、「別の次元を構成しているもの」とは「時間や空間の中にいないのに、生きる存在にとって不可欠なもの」であり、これを[記述の核]とすることができそうです。
[記述の核①] 時間や空間の中にいないのに、生きる存在にとって不可欠なもの
■筆者の意見が書かれている部分を見つける
さらに、―線部の文末に「私は思うのです」と書かれているので、これは筆者の意見であると判断できます。つまり、筆者の意見が書かれている部分を読んでいくと、「別の次元を構成しているもの」をさらに詳しく説明できます。以下で探していきましょう。筆者の意見は―線部の2つ前の段落に書かれています。
[本文]―線(5)の2つ前の段落
目下私は、「無信仰と不信』というシリーズの本を書いています。そこで私が主張しているのは次のようなことです。哲学者とか政治家、科学者とか芸術家とか宗教家など、世界をもう一度みんなが望むような世界に立て直したい、つまり計算に切りつめられてしまうことのない豊かな世界(計算できないってことは、単純でない「むずかしい」ということです)を作りたいと願う人たちなら誰でも、「確固としたもの」が今必要なのだということを考えなければなりません。
「私が主張しているのは次のようなこと」とあるので、次に筆者の主張が書かれていることがわかります。そして「つまり」以降に筆者の主張がまとめられており、「確固としたもの」が必要だと考えていることが読みとれます。よって「別の次元を構成しているもの」は「確固としたもの」であり、これを[記述の核]とすることができるのです。
[記述の核②] 確固としたもの
■[記述の核②]に文をつけ足す
[記述の核②]を具体的に説明し、記述を完成させましょう。「確固としたもの」を具体的に説明している文は先ほど注目した分の続きにあります。
[本文]―線(5)の2つ前の段落
確固としたものと私が呼んでいるのは、今ここに見えるようなかたちでは存在しないのに、それでいて、今ここにいる人たちの生き方によって成り立ち、内実を持っているもののことです。そのものとして存在してはいないのに、生に手応えを与えてくれるような確固としたものを考慮して生きている人たちは、単に生存している状態、つまり生物としての単なる欲求だけで生きている状態を超え出て、自分自身を高めていくことができるでしょう。それが、単なる欲求や衝動に終わってしまわない欲望を持って生きるということなのです。
「つまり」以降に筆者の考えがまとめられており、太字部分を要約すると「単なる欲求や衝動だけで終わらない、自分を高める欲望をもって生きるためのもの」とまとめられます。これを[記述の核②]につけ加えると、以下のようになります。
[記述の核②]に文をつけたした記述
単なる欲求や衝動だけで終わらない、自分を高める欲望をもって生きるための確固としたもの
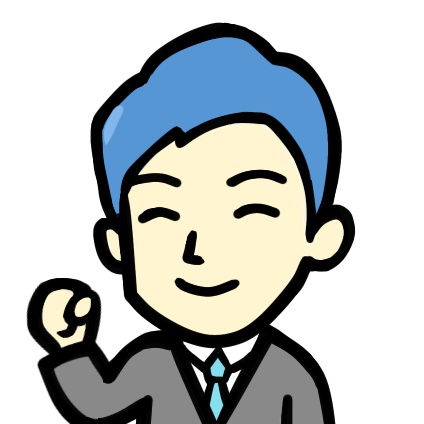
書いてある内容は複雑ですが「つまり」などのまとめの表現がある文に注目すれば、的確に筆者の意見を書くことができます。
■記述をまとめる
上記の[記述の核①]と[記述の核②]に文をつけ足した記述をまとめると、以下のようになります。
[正答例]
時間や空間の中にいないのに、生きる存在にとって不可欠なものであり、単なる欲求や衝動だけで終わらない、自分を高める欲望をもって生きるための確固としたもの。
【2024年度入試】洗足学園中学校 説明文まとめ
今回の説明文では、哲学と宗教の関係や、現代社会での信じることの意味について書かれていました。内容は非常に難しいものでしたが、筆者の意見に注目することで記述問題への答えが見えてきます。
「筆者が何を大切だと考えているか」に注目しながら読むことが、このような文章を理解するための重要なポイントです。
特に、筆者が強調していた「別の次元のもの」は、計算では測れない大切なものであり、それが人間の欲望や社会の向上に欠かせないと述べられています。この「別の次元のもの」を理解するために、子どもたちにわかりやすい例を挙げると以下のようになります。
- 「正義」や「友情」:友達を助けたい気持ちや、悪いことを許せない心は、数字や計算では表せないけれど、とても大切なものです。
- 「夢や目標」:何かを達成したい、叶えたいという思いも、数字にできないけれど、心を動かす大切な力になります。
- 「美しさ」:例えば、夕焼けの景色を見て「きれいだな」と感じる気持ちは、計算では説明できないけれど心に響きます。
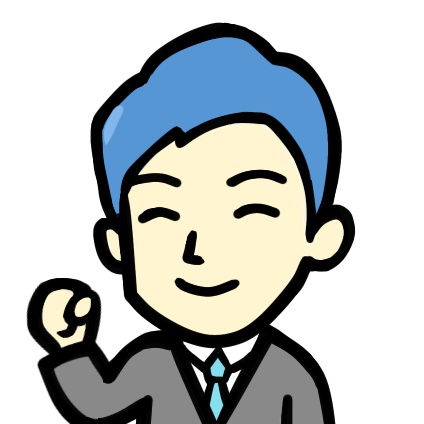
筆者の言う「計算に収まらないもの」は、これらのような心で感じるものや、社会をより良くするための力といえるでしょう。
洗足学園中学校の文章は難解でしたが、このように筆者の意見や例に注目することで、理解が深まり、記述問題にも対応できるようになります。読解力を磨くために、ぜひ日頃から筆者の考えに注目して文章を読み進める練習をしてみてください!
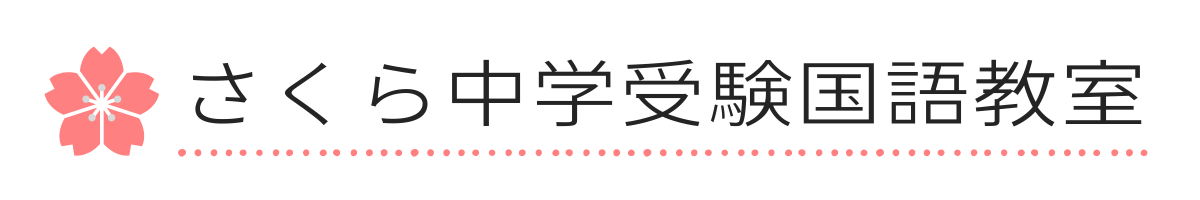
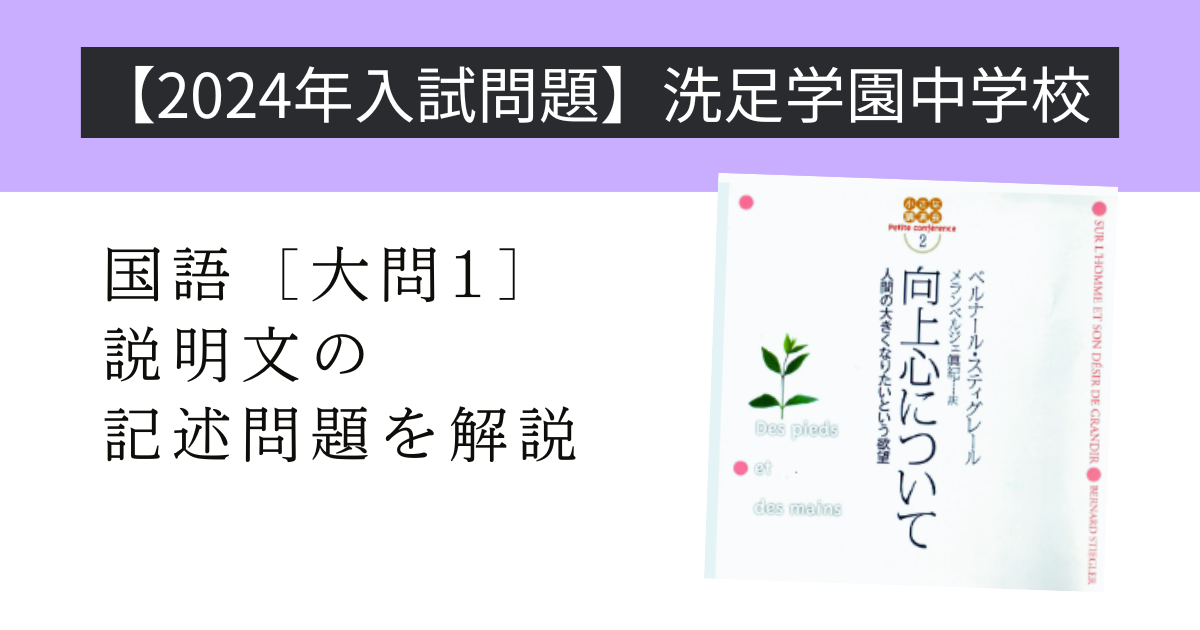

コメント